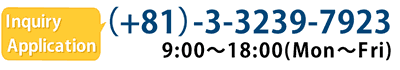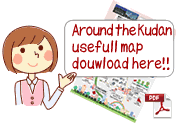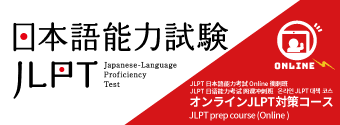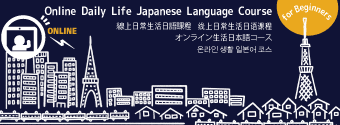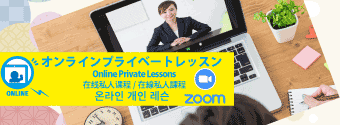「英語対応マニュアルはあるが、そもそも相手が英語話者ではなかった」
今、日本の多くの企業や自治体で、こうした「見えないコミュニケーションの壁」が深刻な問題となっています。
少子高齢化による労働力不足を背景に、外国人材の雇用は不可欠な経営戦略となりました。また、行政サービスにおいても、外国人住民の数は年々増加し、多言語対応は「特別なサービス」ではなく「必須の業務」へと変わっています。
この課題に対し、多くの組織が「英語対応」や「多言語翻訳ツールの導入」といった対策を進めてきました。しかし、現場からは依然として「うまくいかない」という悲鳴が上がっています。
なぜでしょうか?
それは、現場の課題の本質が「英語が話せないこと」ではないからです。
本質的な課題は、「日本語が母国語ではない多様な人々(非英語圏含む)に、日本社会の複雑なルールや業務指示を、誤解なく・迅速に・日本語で伝えられないこと」にあります。
この記事では、多くの組織が見落としがちな「外国人 雇用 コミュニケーション」の本当の難しさとは何かを深掘りし、なぜ九段日本語学院の「やさしい日本語講座」が、その根本的な解決策として今、多くの企業や自治体から選ばれているのかを徹底的に解説します。
あなたの組織は大丈夫? 現場で起きている「コミュニケーション事故」の現実
「うちは英語のマニュアルがあるから大丈夫」「翻訳アプリを使えば問題ない」
そう考えている管理者の方も多いかもしれません。しかし、現場ではすでに「小さな事故」が多発しています。
限界①:「英語対応」という幻想。ベトナム、ネパール、ミャンマー…非英語圏の増加
まず認識すべき現実は、日本で働く外国人材の出身国が大きく変化していることです。
かつては英語圏や英語教育が主流の国からの人材も目立ちましたが、現在の技能実習生や特定技能の分野では、ベトナム、インドネシア、フィリピン、ネパール、ミャンマーといった非英語圏からの人材が大多数を占めています。
彼らにとって、英語は私たち日本人と同じ「外国語」です。
現場のリーダーが、不慣れな英語で一生懸命に指示を出し、相手も不慣れな英語で「Yes」と答える。この「英語の伝言ゲーム」が、どれほど危険なことか。
「英語対応」を進めることは、多言語化の一歩としては重要です。しかし、それだけでは現場の大多数を占める非英語圏の人材とのコミュニケーションは解決しません。
限界②:翻訳アプリ(AI)の落とし穴。「ニュアンス」と「専門用語」は伝わらない
「それなら翻訳アプリを使えばいい」という考えにも落とし穴があります。
近年のAI翻訳の精度は向上しましたが、万能ではありません。
- ① 専門用語・業界用語の誤訳:
建設現場の「玉掛け」、IT業界の「デフォルト」、行政手続きの「課税証明書」。これらをAIが正しく瞬時に翻訳できるでしょうか? 間違った翻訳で伝えた場合、その責任はAIではなく、指示した日本人側にあります。 - ② ニュアンスが消える:
「なるべく早くお願いします(できればで良い)」と「至急お願いします(最優先で必須)」という日本語のニュアンスを、AIは正確に伝えられません。 - ③ スピードの欠如:
行政窓口で、住民とAI翻訳の画面を交互に見ながら会話する。飲食店で、注文のたびにアプリを立ち上げる。このタイムラグが、現場の業務効率を著しく低下させます。
限界③:「担当者まかせ」の属人化。あの人がいないと、組織が回らない
最も深刻な問題が「属人化」です。
「英語が少し話せる〇〇さん」「外国籍の△△さん」といった特定のスタッフに、外国人対応のすべてを押し付けていないでしょうか?
その担当者が休暇を取ったり、退職してしまったりした場合、組織の外国人対応は一瞬で停止します。これは極めて脆弱な体制です。
また、その担当者自身も「自分だけが大変だ」と不満を抱え、離職につながるケースも少なくありません。
本当の解決策とは、特定の「誰か」が頑張ることではありません。
「日本人スタッフ全員」が、簡単な日本語で最低限のコミュニケーションを取れるようになること。
それこそが、強くしなやかな組織を作る唯一の方法です。
【課題深掘り①】自治体・行政窓口:「住民」としての外国人を支えきれない現実
まず、行政サービスにおける課題を深掘りします。
外国人住民への対応は、今や「国際交流課」だけの仕事ではありません。「住民課」「保険年金課」「税務課」「子育て支援課」など、すべての窓口で発生する日常業務です。
課題:複雑すぎる行政用語。「伝わらない」が「命」に関わる
自治体の窓口で使われる言葉は、日本人にとっても難しいものです。
「住民税の更正の請求」「国民健康保険料の減免申請」「児童手当の現況届」「就学時健康診断通知書」…。
これらの複雑な手続きを、日本語学校に通い始めたばかりの外国人住民に、どう伝えればよいのでしょうか。
- ケース1:手続き漏れによる生活基盤の喪失
「転入届は14日以内です」という簡単なルールが伝わらず、在留カードの更新ができなくなる。
「保険料の納付書です」が伝わらず、未納が続いて督促状が届き、パニックになって相談に来る。 - ケース2:緊急時の情報伝達(防災)
「〇〇地区に避難勧告が発令されました」
「ハザードマップを確認し、直ちに高台へ避難してください」
この情報が伝わらなかった場合、それは「命」に直結します。災害時において、翻訳アプリを待つ時間はありません。日本人スタッフが、直接、簡単な言葉で「危ないです!すぐに高いところへ逃げてください!」と叫べるかどうかが、生死を分けるのです。
なぜ「やさしい日本語」が必要か?
自治体に求められるのは「おもてなし」ではなく「公平な行政サービスの提供」です。
英語の通訳者を雇う予算は限られています。全職員が英語を習得するのも非現実的です。
だからこそ、今いる「日本人職員」が、今持っている「日本語」という資産を使って、情報を簡略化して伝える技術=「やさしい日本語」が、最も現実的で、コストパフォーマンスが高く、そして公平な解決策となります。
【課題深掘り②】企業(人事・現場):「戦力」としての外国人を活かせない現実
次に、民間企業、特に外国人雇用を積極的に進めている製造業、建設業、介護業、農業などの現場の課題です。
課題:最大の経営リスクは「安全指示」の不徹底
企業にとって、外国人雇用の最大の課題は「生産性」ではありません。「安全(労災)」です。
日本語の「ちょっとした誤解」が、取り返しのつかない重大事故につながるからです。
- ケース1:安全指示の誤解
現場リーダーが「その機械、まだ触るな!」と叫んだ。
「触るな」は「触る(辞書形)+な(禁止)」という、日本語中級レベルの文法です。
N4レベルの外国人スタッフには「触る」しか聞き取れず、機械に触れてしまい、指を負傷した。 - ケース2:危険予知の失敗
ヒヤリハット報告書が「日本語で書けない」ために提出されない。
「足場が滑りやすかった」「いつもと違う音がした」という小さな危険のサインが共有されず、結果として大事故が発生する。
課題:「教える側」の疲弊と「教わる側」の孤立
安全の次に問題となるのが「生産性」と「定着率」です。
- OJT(オンボーディング)の失敗
「こうやって、サッとやるんだ」
「前にも言っただろ」
指導する日本人も、どう教えれば伝わるか分からず疲弊します。教わる外国人も、指示が理解できず、何度も聞き返すうちに「自分はダメだ」と自信を失い、孤立します。 - コミュニケーション不足による離職
仕事の指示はできても、雑談ができない。
「昨日はよく眠れた?」「週末は何をしたの?」
この何気ない会話がないことで、外国人スタッフは「自分は大切にされていない」と感じ、より給料の高い、あるいは居心地の良い別の会社へすぐに転職してしまいます。
なぜ「やさしい日本語」が必要か?
企業が外国人雇用で成功するために必要なのは、高度な英語力ではありません。
「誰が聞いても一回で理解できる、業務指示」を日本語で伝える技術です。
「緊急停止ボタンを押下せよ」ではなく、
「危ない時、この赤いボタンを押してください」と言い換える。
この技術を「日本人側」が学ぶこと。それが労災を防ぎ、生産性を上げ、貴重な人材の離職を防ぐ、最も確実な「投資」となります。
【課題深掘り③】教育・サービス業:「学生・顧客」を満足させられない現実
最後に、大学・専門学校などの教育機関や、ホテル・飲食店などのサービス業の課題です。
課題(教育機関):複雑な「学生生活」のルール
留学生を受け入れる大学や専門学校の窓口も、自治体と似た課題を抱えています。
「履修登録」「単位認定」「奨学金申請」「在留資格の更新」…。
これらの手続きを、日本語能力がまだ十分ではない留学生自身が行わなければなりません。
- ケース:ルールの誤解による不利益
「必修単位」と「選択単位」の違いが分からず、卒業要件を満たせない。
「資格外活動許可(アルバイトの許可)」のルール(週28時間以内)を破ってしまい、ビザの更新ができなくなる。
学生サポート窓口の職員が「やさしい日本語」を習得することは、留学生を「退学」や「不法滞在」のリスクから守るために不可欠です。
課題(サービス業):多様化する「顧客」への対応
インバウンドが回復し、多くの外国人観光客が訪れるホテル、飲食店、小売店。
ここでも「英語対応OK」だけでは通用しなくなっています。
- ケース:非英語圏の観光客
中国語、韓国語、タイ語、フランス語…顧客の言語は多様です。全言語のスタッフを雇うのは不可能です。 - ケース:ルールの伝達
「温泉ではタトゥーは隠してください」
「この商品は免税対象外です」
「アレルギー物質に〇〇が含まれています」
これらが伝わらないと、大きなクレームや健康問題につながります。
翻訳アプリを介さず、日本人スタッフが指差しと「やさしい日本語」で伝えることができれば、顧客満足度(CS)は飛躍的に向上します。
解決策は「翻訳」ではない。九段日本語学院の「やさしい日本語講座」が選ばれる4つの理由

ここまで見てきたように、現場の課題は「英語」だけでは解決できません。
組織の日本人側が、「日本語を分かりやすくする技術」を身につけることが、最も本質的で、汎用性が高い解決策です。
そして、その技術を学ぶ上で、九段日本語学院の「やさしい日本語講座」が最強のソリューションである理由を4つご紹介します。
理由①:教えるのは「日本語教育のプロ」である現役教師
最大の強みは、「日本語教育のプロフェッショナル」が直接指導する点です。
一般的なビジネスマナー講師やコンサルタントが教える「簡単な話し方」とは、レベルが違います。
私たちは、30年以上にわたり、世界70カ国以上の学生に日本語を教えてきました。だからこそ、
- 外国人が「なぜ」日本語を間違えるのか(例:助詞「は」と「が」の違い)
- どの言葉が「難しく」、どの言葉が「簡単」なのか(例:「会議」より「ミーティング」が簡単)
- どの文法が「伝わりにくい」のか(例:受身形、使役形、二重否定)
を、言語学的なメカニズム(専門性)に基づいて熟知しています。
「なぜ伝わらないか」を知り尽くしたプロが教えるからこそ、現場で本当に「伝わる」技術が身につくのです。

理由②:貴社のための「フルカスタマイズ研修」
本講座は、決まったテキストを読み上げるだけの研修ではありません。
貴社の業種、職種、そして「今、実際に困っている場面」に合わせて、研修内容をゼロから設計します。
- 自治体様なら: 実際の申請書や窓口案内のパンフレットをお借りし、「これをどう『やさしく』するか」をワークショップ形式で学びます。
- 製造業様なら: 実際の「安全マニュアル」や「作業指示書」を教材に、「どう言い換えれば労災を防げるか」を実践的に訓練します。
- サービス業様なら: 現場の「接客マニュアル」を元に、アレルギー確認や禁止事項の伝え方をロールプレイングします。
この徹底したカスタマイズが、研修の満足度と現場での実践率を最大化します。
理由③:「言い換え(リライト)」の実践トレーニング
本講座は「座学」だけではありません。最も時間を割くのが「言い換え(リライト)」のトレーニングです。
やさしい日本語 言い換えの例
- (NG)「土足厳禁」
→(OK)「ここで くつを ぬいでください」 - (NG)「当院では診療できません」
→(OK)「ここでは びょうきを みることが できません」 - (NG)「次回の納期限は5月末日です」
→(OK)「つぎの おかねは 5がつの さいごの ひ までに はらってください」 - (NG)「機械の稼働中は、絶対に手を触れないこと」
→(OK)「きかいが うごいている とき、ぜったいにてで さわらないでください。あぶないです」
このように、実際の職場で使う言葉を「やさしく」する訓練を繰り返すことで、研修が終わる頃には、参加者自身が「やさしい日本語」を作れるようになります。
理由④:柔軟な実施形態(オンライン・派遣・グループ)
研修の実施形態も、貴組織のニーズに合わせて柔軟に対応可能です。
- 講師派遣型 集合研修:
講師が貴社の会議室や現場に伺い、グループワークを中心に熱気のある研修を実施します。 - オンライン研修:
Zoomなどを活用し、全国の支社や多忙なスタッフでも、場所を選ばずに参加可能です。 - プライベートレッスン:
経営者や人事担当者向けに、マンツーマンで集中的に学ぶこともできます。
「やさしい日本語」を導入した組織の未来
「やさしい日本語講座」を組織に導入することは、単なる「福利厚生」や「研修」ではありません。これは、組織の未来を守るための「経営投資」です。
1. 経営リスクの抜本的な低減
安全指示が徹底されることで、労災事故のリスクが最小化されます。行政手続きの誤解がなくなることで、住民との法的なトラブルを未然に防げます。
2. 生産性・サービス品質の向上
業務指示が一度で正確に伝わることで、手戻りやミスが減り、生産性が向上します。顧客への案内がスムーズになることで、顧客満足度(CS)が向上します。
3. 人材定着率の向上と「選ばれる職場」へ
「この会社(職場)は、私の国の言葉や英語が通じなくても、日本人スタッフが分かりやすく伝えようと努力してくれる」
この「心理的安全性」こそが、外国人スタッフの定着率を劇的に改善します。彼らの口コミは、「あの会社は働きやすい」という評判を呼び、将来の採用活動(リクルーティング)においても大きな資産となります。
4. 全スタッフの「スキルアップ」
「やさしい日本語」の技術は、外国人対応だけにとどまりません。
「複雑なことを、簡潔に、分かりやすく伝える」というスキルは、日本人の新人教育、高齢者への対応、顧客へのプレゼンテーションなど、すべてのビジネスコミュニケーションに応用可能な「一生モノのスキル」となります。
お問い合わせから研修実施までの流れ
導入までのステップは非常にシンプルです。
- STEP 1:お問い合わせ
まずは、本記事下部のフォームまたはお電話にて、貴組織の課題やご要望を(漠然としたものでも構いません)お聞かせください。 - STEP 2:ヒアリング・研修プログラムのご提案
当研究所の専門コーディネーターが、貴組織の具体的な業務内容、受講人数、ご予算、目指すべきゴールを詳細にヒアリングします。 - STEP 3:研修内容のカスタマイズ・お見積もり
ヒアリング内容に基づき、貴組織専用のオリジナル研修カリキュラムと、お見積もりを作成・ご提案します。 - STEP 4:研修の実施
決定した日時・形態(オンラインまたは派遣)にて、日本語教育のプロフェッショナルが研修を実施します。 - STEP 5:アフターフォロー
研修実施後も、継続的なサポートや、定期的なブラッシュアップ研修のご相談も承ります。
まとめ:組織の「言葉の壁」を「言葉の橋」に変えるために
「外国人 雇用 コミュニケーション」や「外国人 窓口対応」の課題は、もはや放置できるものではありません。
そして、その解決策は「英語」や「AI」に丸投げすることではなく、私たち日本人自身が「伝える技術」を学ぶことです。
「やさしい日本語」は、コストをかけて特定の通訳者を雇うこと(点の対応)ではなく、組織全体のコミュニケーション能力を引き上げる「面の対応」です。
九段日本語学院は、30年以上の日本語教育の知見(E-E-A-T)を活かし、貴組織の「言葉の壁」を、多様な人材を活かす「言葉の橋」に変えるお手伝いをします。
「うちの業界でも対応できるか?」「まずは話だけでも聞いてみたい」
どんな些細なご相談でも構いません。ぜひ一度、貴組織が抱える課題をお聞かせください。
▼今すぐ組織の課題を相談したい方はこちら
【九段日本語学院】法人・自治体向け「やさしい日本語講座」